カツオを使った代表的な料理と言えばみなさんは何を思い浮かべますか?
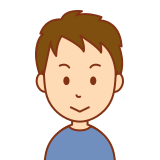
んーカツオのたたきしか思い浮かばない!
大正解!
このように思われた方も多いのではないでしょうか。
4月から5月にかけて食べるカツオのたたきは、脂がすごくのっていて、
非常においしいですよね。いっぱい食べたくなっちゃいます(笑)
そんなカツオのたたきですが、たたきって何だろうって疑問に思ったことはないでしょうか。
そこで今回はたたきの意味とあらいやおつくりの違い、
さらにはお刺身の豆知識についても解説していきたいと思います。
最後まで読んでいただけると嬉しいです。
たたきの意味とは?
カツオのたたきやあじのたたきはほとんどの方が聞いたことあるのではないかと思いますが、
たたきの意味についてはご存知ない方が多いのではないでしょうか。
たたきとは、実はそのままで包丁の刃や峰(背中の部分)、両側で軽くたたいて調理したり、タレや塩を手に付けてたたいて味をしみこませて調理するところから、そういわれるようになったんですね。
ちなみにいつごろからカツオのたたきが食べられていたかと言いますと、江戸時代の中頃からで、
カツオを獲っていた漁師たちが、カツオを炙り、それをを一口大の大きさに切りわけ、塩を振り、包丁でたたいて作った「塩だたき」がはじまりとされています。
しかし、なぜあぶっていたのかと言えば、当時生のカツオを食べた人たちが食中毒にかかって、死んでしまう事がたびたびあったため、領主が生の魚を食べることを禁じたんですね。
それでもどうしてもたべたい!という人たちが、表面をあぶれば、生ではなくなると思ったのがきっかけで、カツオの刺身を再び食べられることに成功したのでした。
なんとか食べたいと思い知恵をしぼって、再度食べられるようにするとは、
とても面白いですね。それがかえって良い結果を生み出したことは言うまでもありません。
[adsense]
おつくり、あらいの違いって・・・・?
この言葉もやたらめったら聞く言葉ではないですが、聞いたことあるのではないでしょうか。
それではこのおつくりや、あらいについても解説していきたいと思います。
おつくりとは
おつくりとは生の魚を切ってお皿に盛り付けたものをいいますが、刺身とは若干違い、
おつくりは魚をきれいにもりつけ、ちゃんと調理してるということを強調している意味合いがあります。
関東ではお刺身と言われることが多いのに対し、関西ではおつくりといわれることが多い傾向にあります。
ちなみに、切るという言葉を使わないのは、どうしてだかわかりますか。
それは武士がいた時代切るという言葉はあまり好ましく思っていなかったため、その言葉は避けて、おつくりとしたとか。刺身もおつくりと同様に「切る」ではなく「刺す」
を使ったという説があります。
あらいとは
つづいてあらいですが、これは鯉のあらいとして聞きなじみのある方が多いのではないかと思います。
あらいとは、魚を薄くそぎ切りや、糸切りにして、冷たい水や氷水にちょっとつけて盛り付けをします。表面に付着している脂分を洗い流すことからこの名が使われるようになりました。
ちなみにこの冷水や氷水にほんの少しつけることで、身がしまり、こりっとした食感を生み出します。
豆知識:刺身はかつて本当に刺していた!?
ここでもうひとつ、刺身にまつわる豆知識を紹介したいと思います。
上記でもさきほど述べたように、武士たちは切るという言葉を嫌ったため、
切るではなく刺すという字を使い、刺身になったという説を解説しましたが、
ほかにも説があり、実はかつてのさしみは、尾っぽを身にさしていたという説があったんです。
驚かれた方も多いと思います。
ではいったいなぜ尾っぽを身に刺していたのかと言いますと、
魚を切るとどの魚だったかがわからなくなってしまうため、
わかりやすいようにさしていたというわけなんですね。
そのため刺身といわれるようになったという説があります。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
今回はたたきの意味やおつくりとあらいの違い、さらには刺身にまつわる豆知識について紹介しました。
もしこれらを食べる機会があったときに、説明できるとすごく格好いいので、
これを機にしっかりと理解してしまいましょう!
それではまた!
最後まで読んでいただきありがとうございました!



コメント