動物園で圧倒的な人気をほこるパンダ。
かわいらしい姿はもちろんのこと、しぐさもとても癒されるものがありますね。
でんぐり返しをしたりするパンダもいるとか。
上野動物園では2017年にシャンシャンが生まれ、大きな話題となりましたね。
僕も見てみたかったのですが、僕が行ったときにはまだシャンシャンは小さくて、まだ公開されていなかったのを覚えています。それが今では大人のパンダと同じほどの大きさになりましたが、
いまでも人気は衰えず、見に来る人たちを楽しませてくれてますね。
そんなパンダですが、熊みたいな姿をしているのに、なんで笹や竹食べているのか疑問に思ったことはないでしょうか。
そこで今回はパンダが笹や竹をたべるのはなぜかについて紹介していきたいと思います。
またパンダにまつわる豆知識も紹介しますので最後まで読んでいただけると嬉しいです。
パンダはなぜ笹や竹をたべるのか・・・・・?
あの体格から、どちらかと言えば、魚や肉を食べそうな感じなのに、なぜ笹や竹を食べるようになったのでしょうか。気になりますね。
その答えは、意外にも生物同士の争いから身を守るために逃げ込んだ場所が笹や竹がたくさんはえているところだったからなんですね。
パンダは肉食動物から身を守るために、どんどん追いやられ、最終的に笹や竹が多く自生しているところに逃げ込みました。そこではそれ以外に食べるものがありません。当然食べなければ、生きていけませんから、仕方なく食べざるを得なかったのがパンダが笹や竹を食べるようになったきっかけなんだとか。
大型の動物なのでキリンみたいに長い時間食べなければならず、なんと14時間で12キロほど
食べているんですね。大食いの人が食べる量よりもはるかにそれをしのぐ量で、
かなり驚きです。
しかし残念なことがあったんです。
それは、パンダの消火器は笹や竹をちゃんと消化できる機能をほとんど
持ち合わせていなかったんですね。消化することのできる量は摂取した量と比べると、
その17%ほど。
草食動物の消火器は植物をたべてもしっかり分解できる機能を持っているので当然のことながら、
問題ないのですが、いかんせんパンダの消火器は、肉食動物と同じようなつくりになっているので、ちゃんと消化できないのは言うまでもないことです。
また草食動物の腸は、繊維質が多い植物を食べているため、馬の腸を例に出すと、
なんと40メートルもあるのに対し、パンダは6メートルしかないんですね。
パンダは本来肉を食べて生きていたのですが、上記でも述べたように途中から笹を食べざるを得ず、それでも長い時間笹を食べてきたのですが、一向に消火器が食べ物に合わせたつくりにならないのは本当に不思議ですし、かわいそうですね。
[adsense]豆知識:パンダの名前の由来
ここでパンダにまつわる豆知識を紹介します。
みなさんはパンダの名前の由来って気になったことはありませんか。
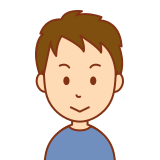
パンダだけにパンと何か関係があったりして!?
安心してください全然関係がないです(笑)
それではいったいパンダの名前の由来とはいったい何でしょうか。
さかのぼること1825年。ヨーロッパ人が調査にあたりネパールを訪問した際、
赤茶色の生き物がいたのであれは何であるかを現地の人に聞いたんです。
そうしたら、現地の人はネガリャポンヤと答えたんだそう。
ネガリャポンヤは日本語に訳すと、竹を食べるもの。
これが時代がたつにつれなまってパンダになったというわけなんですね。
しかしこのときに見つかったパンダはパンダでも風太くんでおなじみの
あのレッサーパンダだったんです!
レッサーパンダが発見された後に、あの白と黒のツートンカラーでおなじみのパンダが発見され、
同じ名前ではややこしいので、大きい方のパンダにはジャイアントパンダと、
そして小さい方のパンダには小さいを意味するレッサーをつけてレッサーパンダとしたんですね。
以上パンダにまつわる豆知識でした!
さいごに
いかがでしたでしょうか。
今回はパンダは笹や竹を食べるのはなぜかについてと、
パンダにまつわる豆知識を紹介しました。
パンダは体のつくりが肉食動物と同じであるけれど、
肉を食べず、笹や竹を主に食べているので、やはりその方が凶暴なイメージがつかず、
優しそうな感じで親しみやすいので結果的にはよかったのかもしれないですね。
それにしても動物園でパンダのでんぐり返し実際に見てみたいものです。
そう思ったら、上野動物園に行きたくなってきました(笑)
それではまた!
最後まで読んでいただきありがとうございました!



コメント