国民的な飲み物と聞かれて、みなさんは何を思い浮かべますか?
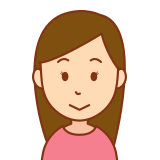
カルピス、ファンタ、コーラかな!
正解です!
どれもみなさんは一度は飲んだことあるんじゃないでしょうか?
それぐらいかなり有名な飲み物ですね。
僕も今でもこれらの飲み物は飲んでおり、たまに変わった味が店頭に並べてあるのを見ると、
すぐ買っちゃうくらい大好きです。
そんな国民的な飲み物ですが、カルピスの名前の由来って気になったことはないでしょうか?
実はある意外なものと関連があったんです!
今回はカルピスの名前の由来について紹介していきたいと思います。
カルピスの名前の由来とは?
みなさんおなじみの飲み物であるカルピスですが、カルピスという言葉は実はある二つの言葉が合わさってできた言葉だったんです。
1つ目は勘が鋭い人はお分かりになられたかと思いますが、カルシウムの「カル」なんですね。
そして2つ目がが仏教とゆかりのあるサンスクリット語のサル「ピス」だったんです。
、
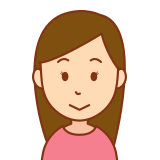
えー!意外!
全然考えもつかなかった!
本当ですね。僕もまさか仏教と関連してるなんて夢にも思わなかったです。
それではいったいどういうことなのかといいますと、
仏教において、「乳味・酪味・生酥(しょうそ)味・熟酥(じゅくそ)味・醍醐味(だいごみ)」のことを五味といいます。これは牛のミルクの味を表しており、、上記の順に味がどんどん良いものとなっていきます。
そして、この中で最高の味を表す醍醐味をサンスクリット語で言うと、サルピルマンダとなり、カルシウムと合わせるとサルピルとなって、響きがあまりよくありません。
どうすればいいものだろうと、カルピスの創業者である三島海雲(みしまかいうん)さんは、
サンスクリット語スペシャリストである渡辺海旭(かいきょく)さんや赤とんぼを作曲したことで知られる音楽家の山田耕筰さんにアドバイスをもらいに行きます。
そうすると、醍醐味の次に良い熟酥味に
したらどうかとアドバイスをいただき、熟酥味はサンスクリット語で言うと、「サルピス」というところから、カルシウムの「カル」とサルピスの「ピス」が合わさって、
カルピスという言葉がついに誕生したのです。
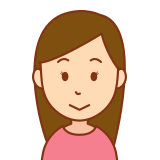
なるほどねえ。
もしや、物事の深い味わいを表すだいごみって
仏教が由来だったの?
そうなんです!
五味において最高の味という意味がある醍醐味が転じて、そのような意味になったんですね。
[adsense]豆知識:日本ではカルピスだけどアメリカでは?
日本ではカルピスと言われていますが、果たしてアメリカでもカルピスと言われていると思いますか?
答えはノーです。
実はアメリカでは「カルピコ」と呼ばれていないんですね。
なぜかというと、アメリカ人がカルピスを発音したとき、
アメリカ人にはカウピスと聞こえてしまい、
日本語に訳すと牛の尿という意味になり、下品に聞こえてしまうので、そういうわけで、
カルピコと言われるようになりました。
豆知識2:パッケージの水玉模様は何を表している?
カルピスのパッケージをよく見ると、水玉模様がデザインされているのに
気づいた方も多いでしょう。
ではその水玉模様はいったい何を表しているのでしょうか?
答えは、星を表しています。
カルピスが誕生したのは1919年7月7日のこと。
7月7日ときたら、何のイベントがあるかもうご存知ですよね。
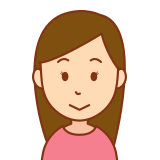
七夕ね!
大正解です!七夕ですね。

七夕の日天の川の近くに住んでいた織姫と彦星が一年に一度だけ会うという有名なお話がありますが、この天の川をヒントに夜空にまたたく星をデザインしたとか。
また当時のパッケージは今と逆で青地に白い色の水玉模様だったんですね。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
今回はカルピスの名前の由来について紹介しました。
カルピスは仏教と深いかかわりがあることがわかりましたね。
カルピスは飲み物としてももちろん大人気がありますが、
かき氷のシロップにもよく使われていて、暑い時期にカルピスを氷にかけて食べると、
とてつもなくおいしいですね。
かき氷の話をしていたらかき氷が食べたくなってきました(笑)
久々に家でかき氷を作ってみたいです。
それではまた!



コメント