一般的にお彼岸になると、スーパーなどで売りだされるぼたもちやおはぎ。
子供のころ、親がよくおやつに出してくれたのですが、あんこが苦手な僕は黄な粉でくるまれたものをよくたべたものです。懐かしいですね。
そんなぼたもちとおはぎですが、みなさんはこれらがどう違うか説明できますか?
今回はぼたもちとおはぎの違いについて紹介していきたいと思います。
ぼたもちやとおはぎの違いとは?
ぼたもちとおはぎの違いは?と聞かれて
「ぼたもちはこしあんを使用して、おはぎはつぶあんを使用している」と思った方いませんか?
実は違ったんですね。
ぼたもちとおはぎの違いは簡単に言えば、いつ食べるかによって名前が変わるというものなんです。

ぼたもちを漢字で書くと「牡丹餅」と書きますが、牡丹(ぼたん)という花が含まれています。
この花が開花する季節はちょうど春なので、春のお彼岸の時には、ぼたもちと呼ばれます。

対して、おはぎは、「お萩」と書き、萩(はぎ)という花が含まれていますね。
この花が開花する季節はちょうど秋なので、秋のお彼岸の時には、おはぎと呼ばれるわけなんです。
ちなみに、なぜ牡丹や萩が使われるようになったのかといいますと、
小豆の粒がその季節に開花する牡丹や萩のようにみえることからこの名前があてられたんですね。
[adsense]
お彼岸にどうしてぼたもちやおはぎを食べるのか?
ぼたもちとおはぎの違いは上記の説明でわかりましたね。
ではどうして、お彼岸にぼたもちやおはぎを食べる風習があるのでしょうか?
その答えとは、厄除けの効果があったからなんです。
小豆は魔よけの色である赤い色をしているため、古くから災いがおきないようにする
効果があるといわれていました。
そして、あずきで作ったぼたもちやおはぎをご先祖様にお供えすることで、
災いがふりかからないようにしたのが、はじまりだといわれています。
[adsense]
春夏秋冬によって呼び名が違う?
春はぼたもち、秋はおはぎと季節によって呼び名が違うことはさきほど述べました。
しかし、実は春秋以外にも呼び名があったんですね。
夏は夜船
夏は「夜船(よふね)」というんですね。

というのも、
ぼたもちはおもちと製造方法が違い、すりこぎを使用して、作ります。
そして、餅をついたときにぺったんぺったんという音が出ないので、周りには音が聴こえません。
そこから搗(つ)き知らずとなり、さらに言葉遊びをして着き知らずとなり、
夜は暗いため船がいつ着いたのかわからないということで、夜船となりました。
冬は北窓
続いて冬は北窓と言います。
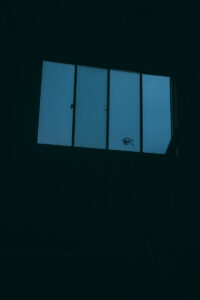
こちらも、さきほどと同様に、搗き知らずから言葉遊びをして月知らずとなり、
月を見ることができないのは北の窓ということで、北窓と言われるようになりました。
昔の人は非常にしゃれていますね。
まとめ
今回はぼたもちとおはぎの違いについて、紹介しました。
まとめると以下の通りです。
ぼたもちのおはぎの違いは季節によって呼び名が異なるだけで、同じものです。
春はぼたもちで、秋はおはぎです。
このことを調べる前に、僕はてっきりぼたもちとおはぎは別なものだと思っていたので、
非常に勉強になりました。
春夏秋冬によって呼び名が違うというのはおもしろく、とてもしゃれていますね。
それではまた!
最後まで読んでいただきありがとうございました。



コメント